5カ年計画である中期経営計画2022も折り返しを迎えました。
社外取締役の視点から、事業基盤の強化と変革の実践の進捗状況や課題感について対話を行いました。

(左から)
社外取締役 注連 浩行 ユニチカ株式会社代表取締役会長を経て、2024年から現職
社外取締役 加藤 広之 三井物産株式会社代表取締役副社長執行役員を経て、2021年から現職
社外取締役 折井 雅子 サントリーウエルネス株式会社専務取締役、公益財団法人サントリー芸術財団総支配人を経て、同財団シニアアドバイザーを務める。2020年から現職
社外取締役 黒田 由貴子 ソニー株式会社を経て、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの顧問・ファウンダーを務める。2022年から現職
社外取締役 池川 喜洋 三菱ケミカルホールディングス代表執行役を経て、2024年から現職
加藤 大林グループの取締役会は社外取締役が過半を占めており、推薦委員会や報酬委員会といった諮問機関についても同様の構成となっています。日本企業の中でも先進的な体制であり、透明性も高く確保されている印象です。
折井 取締役会を中心に取締役座談会や各種委員会といった多層的なガバナンス体制が機能することで、企業全体としてのガバナンスは確実に前進してきたと感じています。議論を重ねる中で、それぞれの役割や位置付けが確立され、実効的な議論が展開されるようになってきていると実感します。
黒田 大林組は2025年4月に社長兼CEOの交代という大きな節目を迎えましたが、推薦委員会や報酬委員会において交代プロセス全般にわたり率直な議論が交わされたことは2024年度の特筆すべき点と受け止めています。
注連 社長兼CEOの交代に際し、推薦委員会において後継者候補の育成状況を確認し、透明性のあるプロセスの下で選定を行いました。今後も次世代の経営を担う人材の育成により、一層注力していく必要があると思います。
池川 新たな経営体制の下、業務執行責任の明確化および迅速化が可能となるCxO制度の導入や、執行役員のさらなるモチベーション向上を図る人事評価制度の制定、サステナビリティとビジネスの収益性向上の共存を目指したKPIの設定などの議論を深化させる必要があると考えています。
黒田 2024年度の取締役会の実効性評価結果によると、取締役会がより実質的に機能していることが示されましたが、その要因の一つに取締役座談会の存在が挙げられます。この制度は私が大林組の取締役に就任した2022年に始まったもので、執行側での検討がまだ煮詰まっていない段階で議論の俎上に乗り、率直な意見交換を通じて、中長期の目線で執行側と経営側の考えを擦り合わせる機会となっています。
折井 2024年度の取締役座談会では、2024年3月に公表した新たな資本政策の実行に加え、人的資本や知的資本の在り方についても議論しました。これらは企業価値の中長期的な向上に密接に関わるものであり、今後も継続的に議論を重ねたいと思います。
加藤 取締役座談会は取締役会を補完する役割として、議論に深みをもたらしています。一方、課題もあると考えます。現在は取締役座談会でさまざまなテーマが議論されていますが、より多くの議案を取締役会で扱う方向性が望ましいと考えています。取締役会と取締役座談会で扱うべきテーマの線引きは難しいところですが、例えば、取締役座談会では、個別案件ではなく、次期中期経営計画や事業ポートフォリオの在り方など、より中長期的かつ多くの議論を要するテーマに焦点を当てることが望ましいと考えます。
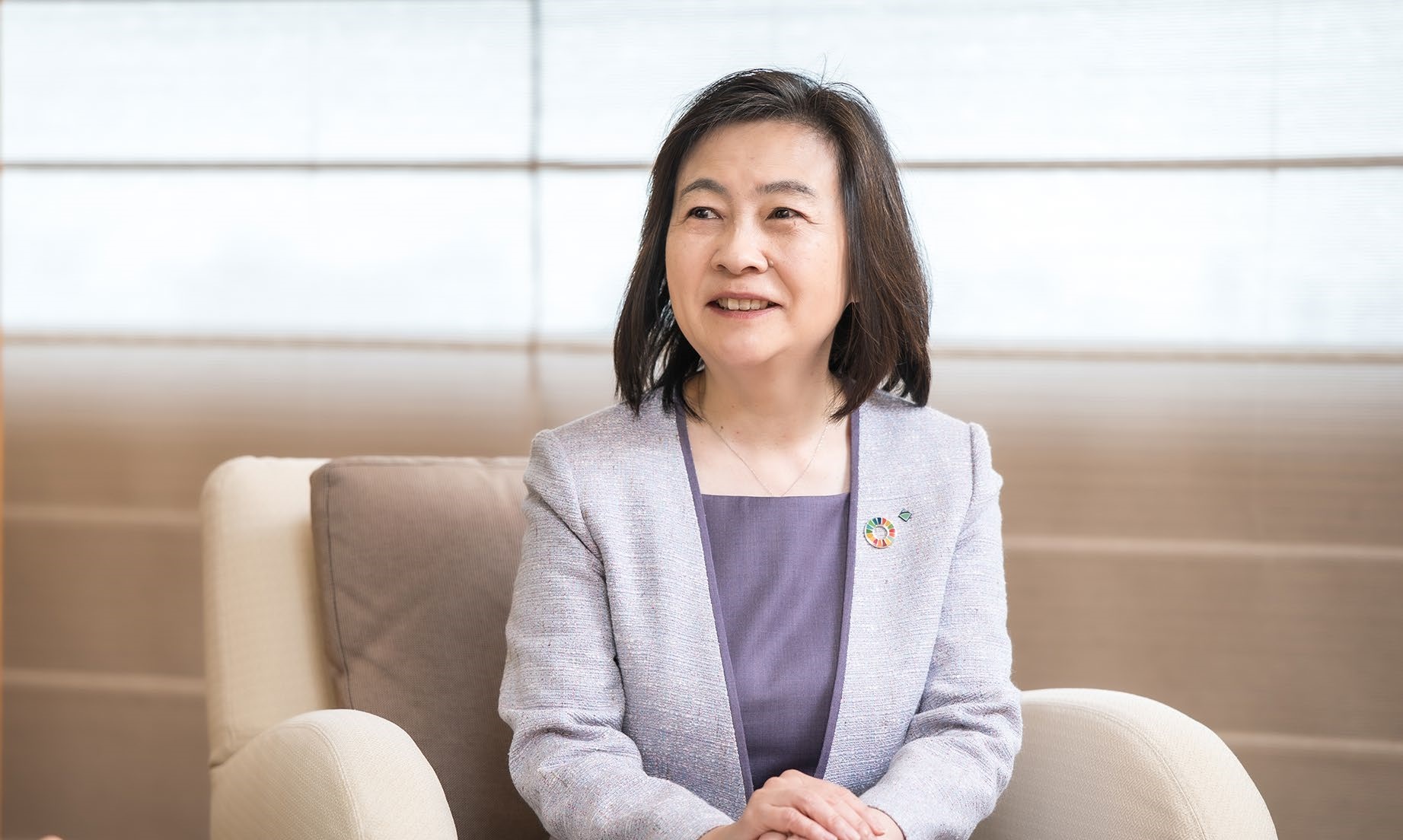
折井 2024年5月に公表した「中期経営計画2022 追補」(以下、中計追補)の基本戦略の冒頭に改めて据えたように、「安全と品質の確保」は引き続き大林グループの最優先課題です。これまでも建設現場でさまざまな対策が講じられていますが、組織風土・人材・技術・サプライチェーンなどの全社的な課題と重ねて、さらに本質的な議論を求めたいと思います。また、中計追補で大林グループの持続的成長の方向性「国内建設事業を中核とし、それ以外の事業が国内建設と同等以上の業績を創出する」が明確に打ち出された意義は大きいと考えており、目指す事業ポートフォリオに照らし合わせ、M&A、開発事業、グリーンエネルギー事業、新領域ビジネスなどの戦略を、個々ではなく全体で評価していくことも今後の課題です。中核の国内建設事業も含めたグループ全体の事業展開においてカーボンニュートラルとウェルビーイングを価値創出のカギと位置付け、今後の成長戦略についてさらに議論を深めていくべきだと考えます。
注連 中核の国内建設事業では、中長期的に建て替えやインフラ再整備の需要が見込まれており、今後も安定的な受注が期待できます。また、海外建設事業も成果が着実に表れてきており、今後、人材育成や体制強化に注力することで、安定的な収益基盤に成長させることが可能です。さらに、世界的にも注目されるグリーンエネルギーや、データセンターといった成長分野への投資を加速させ、次世代の収益の柱として育成することが持続的成長の実現に資すると考えます。
黒田 取締役会では、国内建設事業以外の分野をいかに拡充していくかという点に、相当な時間と議論が費やされています。ROICなどの収益性指標の評価は当然の前提として、本業とのシナジー、大林組の強みの活用、異分野の事業を推進できる人材の確保といった非財務的要素も重視すべきです。大林組がその事業における「ベストオーナー」に足りうるかどうか、常に念頭に置いて推進する姿勢が不可欠です。
池川 ポートフォリオ戦略の議論においては、重点投資事業の選定や市場成長性を踏まえた地域戦略を資金力・事業推進力・技術力・時間軸といった、多様な観点から総合的に議論する必要があります。また、「Obayashi Sustainability Vision 2050」に基づく新規事業の選定に加えて、既存の建設事業に求められる「質の変化」への対応策も欠かせません。地域戦略としては、北米やタイ・シンガポールをはじめとした、すでに展開している地域での拡大、あるいは新規市場の開拓についてもさらなる検討を進めるべきです。M&Aにおいても、こうした総合的な戦略の中でターゲットを選定すべきであり、投資基準として資本コストを上回る水準に照らして、成果が見込めない事業については売却・撤退を含む厳格な規律を設けることが必要です。
黒田 事業領域の拡大に伴い、グローバルおよびグループ会社におけるガバナンス体制の強化も、喫緊の経営課題となっています。
加藤 そうですね。グル ープ全体として、グローバルにおける収益力をいかに高めるかが、今後の成長戦略の中核を成す課題です。その上で、連結子会社、中でも海外子会社の適切なガバナンス体制の構築は、現時点での大きな経営課題の一つと言えます。加えて、その体制を機能させるためには、ボードメンバーとして現地で子会社の経営に深く関与し、グリップを利かせることができるリーダー人材の確保が今後の成長を左右するでしょう。次世代を担う経営人材の育成こそがグループのさらなる成長のカギになると考えています。

加藤 大林組単体の建設事業は、言うまでもなくグループの中核であり、着実に実績を重ねてきました。国内市場の受注環境は現在良好ですが、この状況に甘んじることなく、グループ全体としてグローバルに収益力を強化したいと考えています。現状の海外建設事業、開発事業、グリーンエネルギー事業といった事業群は、はたして大林組にとって最適なのか。どのようなポートフォリオが適切なのか。グループをグローバルで司るガバナンスをどのように強化すべきなのか。これらについては、次期中期経営計画に向けて議論する必要があります。
注連 加藤さんと同じく、ガバナンスの強化がボードメンバーの重要な役割の一つと考えています。取締役会などにおいて、社外取締役として独立した立場で、企業価値向上に資する多様な助言や提案を行うことが必要です。経営陣の意思決定プロセスを俯瞰し、適切に監督・牽制の役割を果たすべく、常に自らの姿勢を問いただしながら向き合っています。
折井 取り巻く環境の変化の大きさ、速さ、複雑さにさらされる中で、変化の意味をリスクと機会の両面で的確に捉え、対応していくことが求められます。そのような環境下だからこそ、基本理念やビジョンを改めて軸に据え、ぶれずに持続的成長の道筋を追求する姿勢が重要です。私自身、建設現場の視察や社員の皆さんとの対話を通して、技術力の高さや人材の強靭さ・豊かさを感じてきました。大林グループが培ってきたこの大きな強みを一層発揮して価値の創出につなげるとともに、その強みと価値を社会に対して的確に訴求していくことに貢献したいと思います。
池川 企業価値の向上には、財務価値の持続的成長が不可欠です。私たち社外取締役は、執行側が練り上げ実行する事業戦略が大林組の掲げるビジョンや価値観に沿ったものか、社会からの期待や要請に応えるものか、潜在的なリスクを含んでいないかといった観点から、独立性を保ちながら客観的に点検する役割を担っています。そして、財務価値にとどまらず、人的資本や技術力といった非財務的価値にも目を向けるべきだと思います。こうした価値を投資家も含めたすべてのステークホルダーに対して、いかに有効に訴求するかを執行側との議論を通して構築することも重要な役割と考えています。
黒田 私も池川さんと同様、中長期的な企業価値向上における重要課題である非財務的価値について、より積極的に意見を申し上げていきたいと考えています。とりわけ、労働力不足に伴う生産性向上、社員のリスキリング、ダイバーシティ推進といった課題に加え、脱炭素、循環経済といった社会的要請をいかに事業機会として転換していくかが 問われています。こうした取り組みをより有機的に結び付け、社外からの視点での対外発信の在り方も含めて支援していきたいと考えています。

折井 社外取締役として、企業が内側に閉じることなく、その輪を外に向けて開くことを役割として意識してきました。さまざまな変化が同時進行する時代において、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまの期待への感度を高め、今後もこうした期待を的確に捉えながら、中計追補で掲げた成長戦略の着実な実行に向けて臨みたいと思います。2024年5月に提示した資本政策における議論では、株主還元と成長投資の両立が課題と申し上げました。引き続き、短期的な動きと中長期の展望の双方を見据えた、バランスの取れた資本政策の在り方を追求していきたいと考えています。
池川 大林グループは、長年にわたり国内外の建築物やインフラ整備事業などを通して社会に大きく貢献してきました。現在は中計追補の遂行で、株主還元や資本政策を強化し、ROEやPBRの改善にも成果が見られています。今後も、株主還元と持続的成長戦略の両立を軸に、社会課題に挑む事業の収益性向上や市場でのプレゼンス拡大を目指します。さらに、事業ポートフォリオ戦略に加えて、ガバナンスの進化や人材資本の強化・ダイバーシティなどの非財務的価値の向上についても、執行側との対話を通じて多面的に議論し、施策に反映させていく所存です。その過程においては、株主・投資家の皆さまと対話を重ね、ご意見を真摯に受け止めながら企業価値の向上に努めていきます。
黒田 社外取締役の役割は、企業価値向上の観点から経営を客観的に監督することにあると心得ています。そのために、資本効率が最適化されているか、将来に向けた明確な成長ストーリーを描けているか、そしてそれに向けた適切な投資判断がなされているかを中心として、その監督に尽力します。
注連 持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、社外取締役として経営の監督と助言の機能を適切に果たしていくことが私の責務です。特に、中計追補で示された施策の進捗状況を確認し、M&Aや戦略的投資案件に対しては、その実現可能性やリスクへの対応状況を注視しています。また、対話を通じて経営陣と市場をつなぐ懸け橋となり、株主・投資家の皆さまとの信頼関係の構築に寄与することも、社外取締役に求められる重要な役割だと捉えています。
加藤 2024年度は想定を超える収益を上げることができ、好調な1年となりました。これはひとえに執行側の尽力の賜物ですが、一方でまだまだ伸びしろはあると感じています。私たち社外取締役は、取締役会やその他の機会を通じて、株主や社員といったステークホルダーを代表して執行側の取り組みを適切にモニタリングし、改善を促す責務を担っています。その点において、ステークホルダーの皆さまの声に真摯に耳を傾ける機会は、株主総会に限らず、より多様な場で継続的に設けていくことが望ましいと考えています。ステークホルダーとの距離は今以上に近くあるべきであり、私たちの問題意識や期待をより発信していくことも検討していきます。

2025年8月


